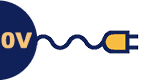|
|
箸 (はし : Chopsticks) |
 |
|
蕎麦を食べるための、最も基本的な道具のひとつ。
箸にはさまざまな種類がある。多様な箸の中で、蕎麦を食すための箸としては杉の割り箸を最上としたい。
|
|
 |
|
箸置き (はしおき : Chopsticks rest) |
 |
|
小さな道具ではあるけれど、さまざまな蕎麦器の調和の中では無視できない。
自然石から銀細工まで、実に多様な種類がある。遊ぶ気持ちで選びたい。
|
|
 |
|
汁つぎ (つゆつぎ : Sauce bottles) |
 |
|
蕎麦つゆを供するための容器。
一人用から多人数用まで、さまざまな形があり、洋食器の応用もあれこれの工夫ができる。
"Sobaware"の中でも、最も強い個性を放つ器のひとつ。
|
|
 |
|
薬味入れ (やくみいれ : Condiment container) |
 |
|
山葵、大根、葱などの薬味を供するための器。
脇役だが、その選択にはずいぶんと悩まされる。難しい。でも逆に冒険もできる。
|
|
 |
|
蕎麦猪口 (そばちょく : Dipping cups) |
 |
|
そば汁を入れ、蕎麦をひたすための器。
決して"Sobaware"の主役ではないのだが、蕎麦猪口のコレクターは少なくない。
"Sobaware"の多様性を代表するものだからだろう。
|
|
 |
|
粉入れ (こいれ : Flour container) |
 |
|
世間には馴染みがない道具(ぼくしか使っていないかも知れない)。
蕎麦を供する前に、本日はこんな蕎麦粉で打ちますよということを明らかにするために、蕎麦粉を供する。そのための器。
|
|
 |
|
湯桶 (ゆとう : Pitchers for soba-yu) |
 |
|
蕎麦湯を提供するための道具。
蕎麦の最後に登場する"Sobaware"。湯桶探しは、実はとても楽しい。あれこれの器から応用できるから。
|
|
 |
|
器 (うつわ : Tray) |
 |
|
蕎麦を提供するための器。
冷たい蕎麦は、必ず蒸篭(せいろ)や笊(ざる)で提供するもの、と決まっているわけではない。蕎麦の器は、もっともっと自由なものだ。
|
|